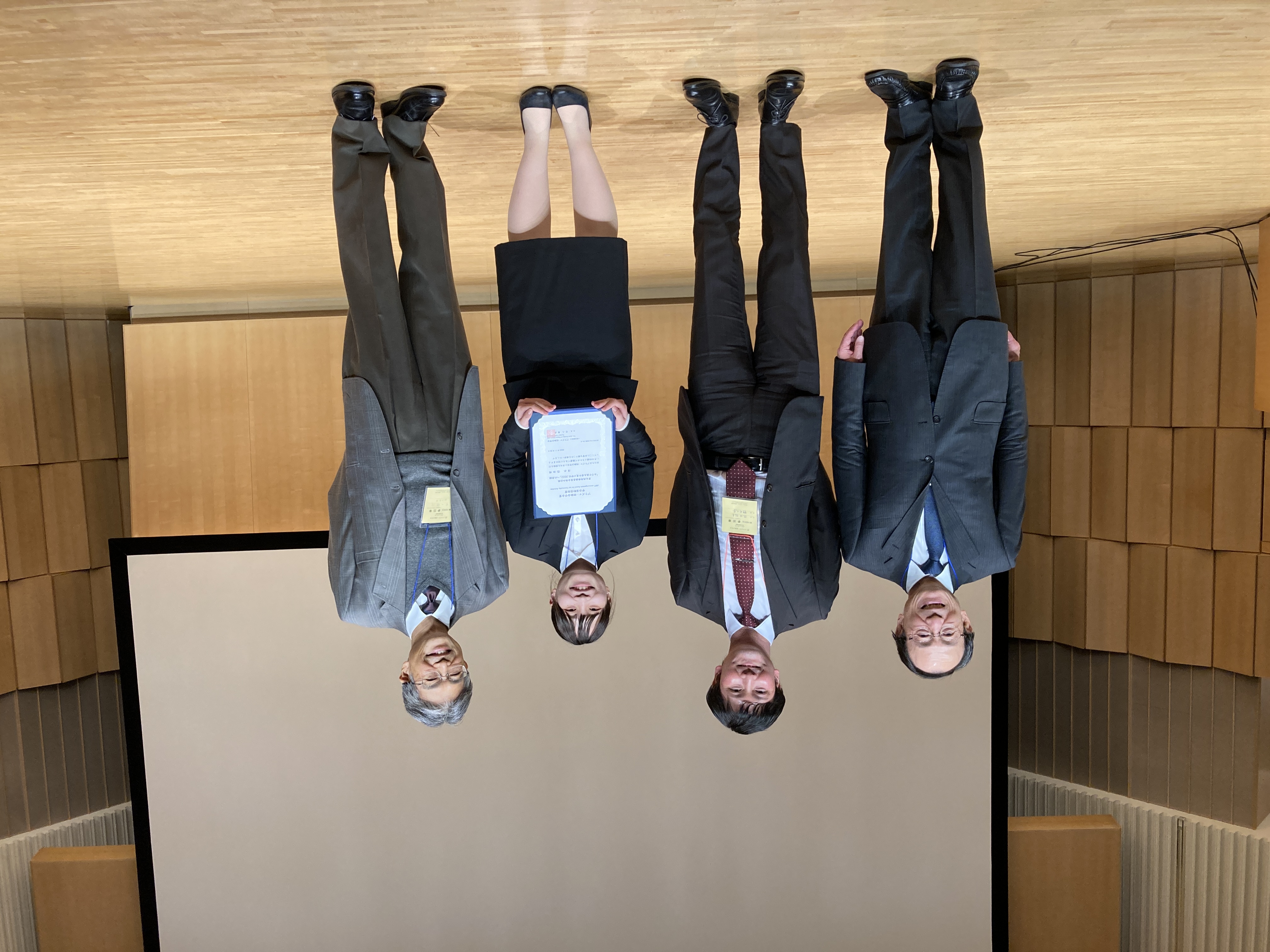第 27 回 技術進歩賞
「先進核融合装置プラズマ加熱用低周波数ジャイロトロンの開発研究」
受賞者: 假家 強(筑波大),南 龍太郎(筑波大),今井 剛(筑波大学名誉教授),出射 浩(九大),恩地拓己(九大)
* プラズマ・核融合学会誌 Vol.93, No.3, 146-149 (2017) 他

「先進核融合装置プラズマ加熱用低周波数ジャイロトロンの開発研究」
受賞者: 假家 強(筑波大),南 龍太郎(筑波大),今井 剛(筑波大学名誉教授),出射 浩(九大),恩地拓己(九大)
* プラズマ・核融合学会誌 Vol.93, No.3, 146-149 (2017) 他

「過渡的・突発的プラズマ現象解明に向けた高時空間分解能トムソン散乱計測装置の開発」
受賞者: 安原 亮(NIFS),舟場久芳(NIFS)
* 第 38 回年会招待講演 23Ca01 (2021) 他
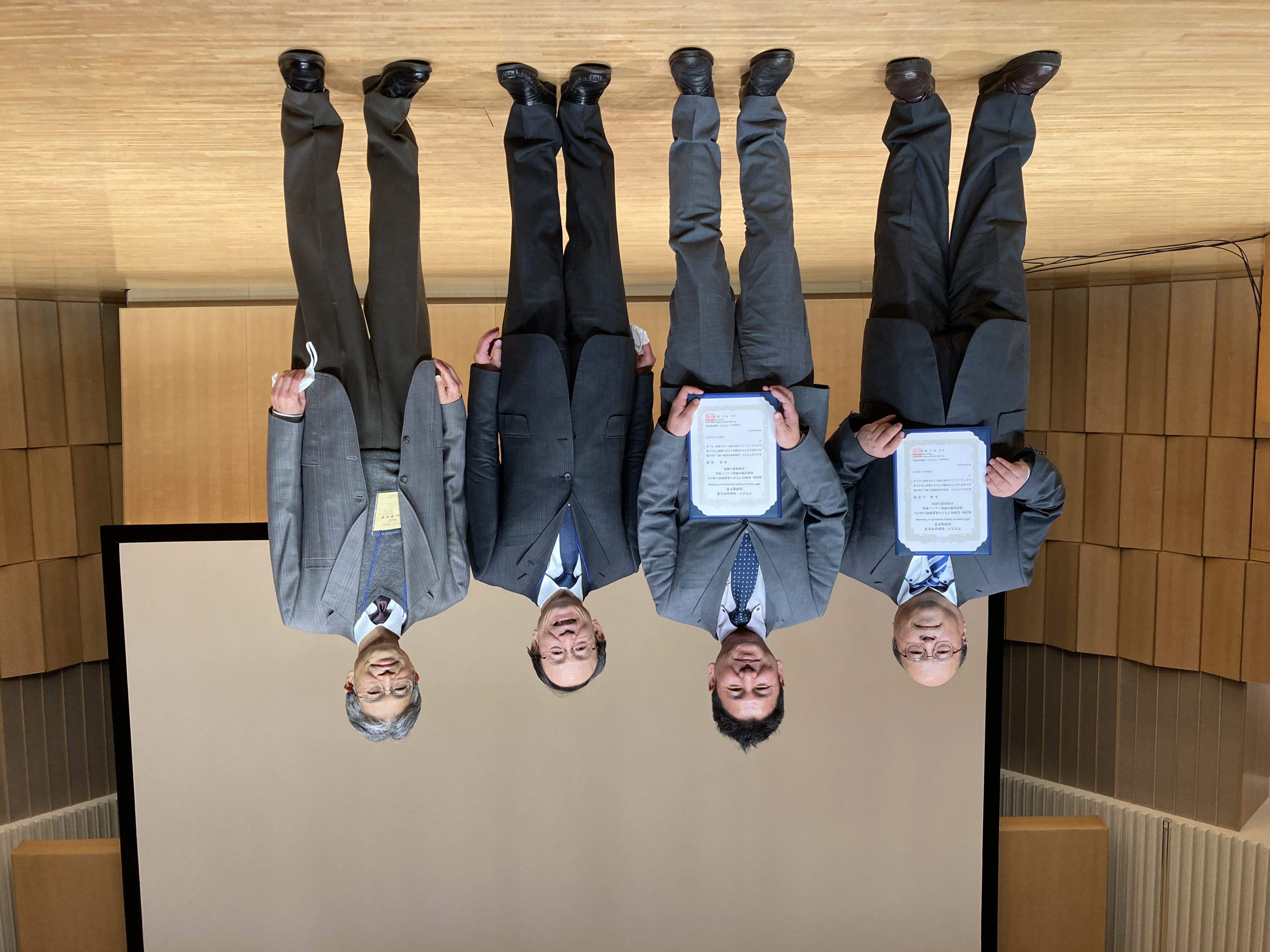
「微粒子に蓄積するトリチウムの測定技術開発と JET で生成されたダスト分析への適用」
受賞者: 芦川直子(NIFS),大塚哲平(近畿大),鳥養祐二(茨城大),朝倉伸幸(QST),増崎 貴(NIFS)
* プラズマ・核融合学会誌 Vol.96, No.1, 2-5 (2020) 他

受賞者:成田絵美(QST)
「機械学習を用いた核融合プラズマの乱流輸送モデリング」
*第 38 回年会招待講演 24Cp01 (2021) 他

受賞者:清水悠加(静岡大)
「「男女共同参画委員会参加企画「女子中高生若手夏の学校 2022」への貢献」 」